

岡山大学「桃太郎フォーラム2025」で学びの未来を探るシンポジウム開催
桃太郎フォーラム2025が岡山大学で開催
2025年9月29日、岡山大学津島キャンパスにて「桃太郎フォーラム2025」が開催され、学内外から約100名の参加者が集まりました。本フォーラムは、学生が思考する能力を高めることを目指したテーマで、28回目の開催を迎えました。
フォーラムの概要
フォーラムは、岡山大学の学長那須保友のもと、教学企画室主催で行われました。開会に際して、教学担当の菅誠治理事が挨拶を行い、文部科学省高等教育局の石川雅史氏が来賓あいさつを行いました。昨今の教育政策や学生の思考能力向上の重要性が強調されました。
その後、田中岳副学長が「感じる」「思う」「考える」という学生の成長過程を説明し、個人思考と集団思考のバランス、および発想や対話の重要性について議論を展開しました。
事例報告
フォーラムでは、さまざまな教育機関の事例報告が行われました。早稲田大学の小川慎二郎氏が、自校の探究プログラムの取り組みを紹介し、生徒の主体的な学びを支援する方法について説明しました。特に、物理教育の観点から生徒のモチベーションを高める工夫が印象的でした。
また、本学の課題探究科目「知の探研」についても学術研究院の教授が、具体的な授業設計とその成果を紹介しました。多様な学部の学生が一緒に学ぶことの意義も強調され、教育の新たな展開が期待されます。
大学院環境生命自然科学研究科の森紀華さんは、台湾での海外研修プログラムに参加した経験をもとに、スキル向上につながる示唆を報告しました。大学院生としての視点から国際的な学びの重要性を語り、研究活動への影響についても触れました。
ラーニングコモンズの進展
関西大学の岩﨑千晶教授による発表では、学習環境のデザインに関する新たな視点が共有されました。ラーニングコモンズの利用方法を具体例を交えながら説明し、学生の思考を促すための支援方法について議論が行われました。
フォーラムの後半には、パネルディスカッションが開催され、東京大学の福留教授が思考に関する基本的な視点を提供しました。教育における知識のあり方や、混ぜる・混ざることの重要性についての意見が交わされ、参加者同士の活発な意見交換が行われました。
参加者の声
フォーラム終了後の参加者アンケートでは、90%以上が「満足」または「やや満足」と回答し、事例報告に対する評価も高かったことが示されました。「多様な分野の学生が混在することの重要性が理解できた」「有意義な内容だった」との声も寄せられ、今後の活動への期待が寄せられています。
まとめ
岡山大学の「桃太郎フォーラム2025」は、これからの教育のあり方や学生が思考するための支援を考える貴重な機会となりました。学生の成長を促すための取り組みが今後も続けられることを期待します。フォーラムは盛会のうちに閉幕し、次回の開催への期待が高まります。
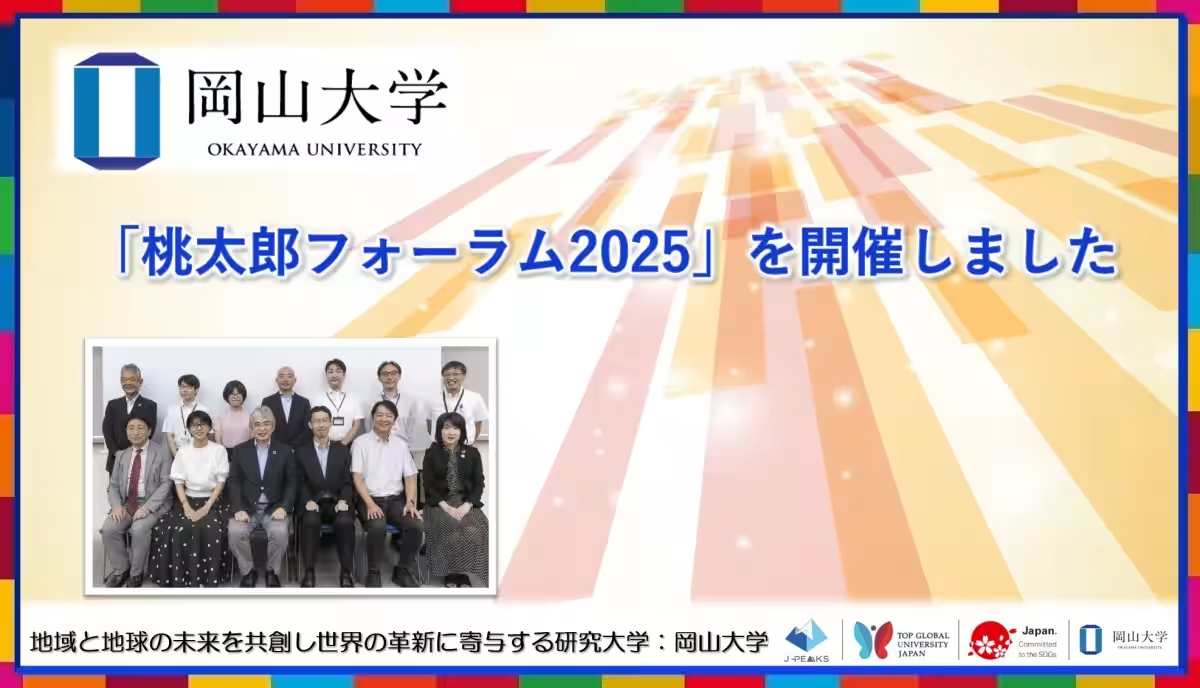






トピックス(その他)



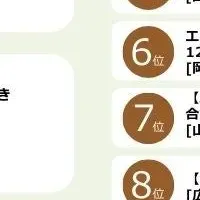
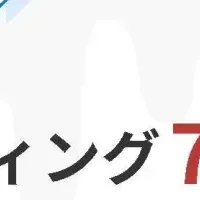
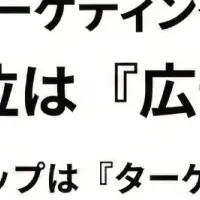


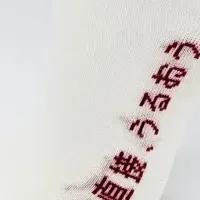
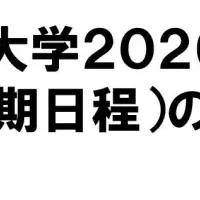
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。