
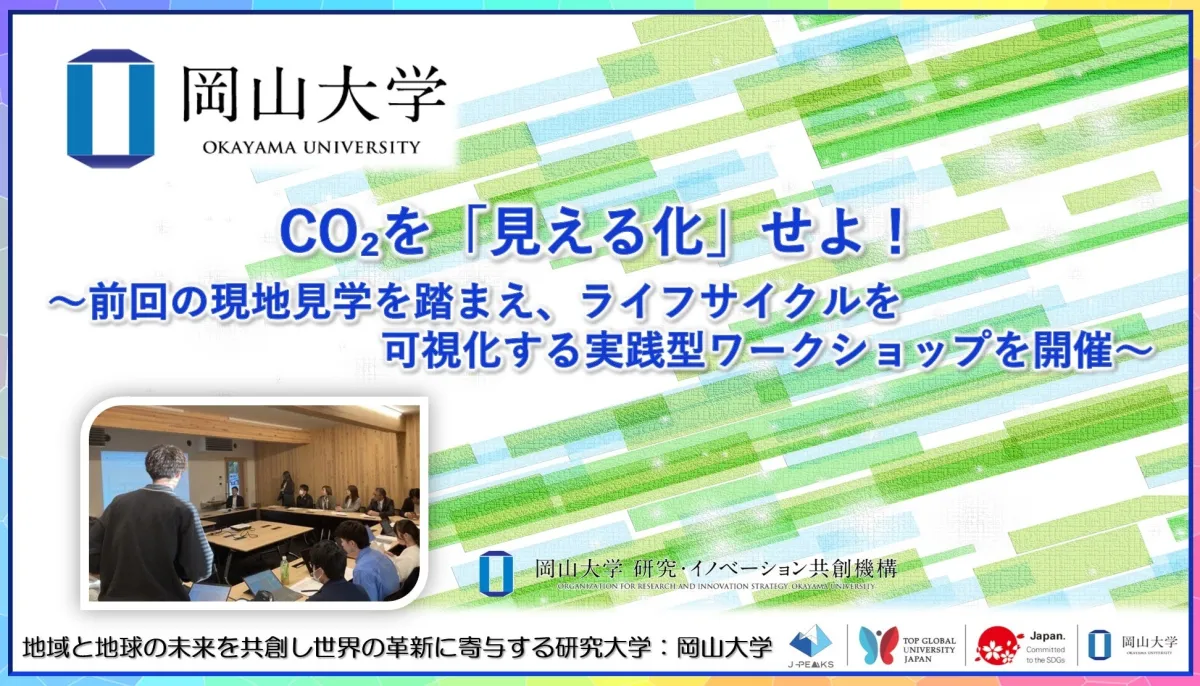
岡山大学の学生が地域企業と共にCO₂排出の可視化に挑む取り組み
岡山大学が挑むCO₂排出の可視化プロジェクト
国立大学法人岡山大学は、2025年11月10日、岡山県商工会連合会との協力により、地域の企業との連携を強化し、CO₂排出量の可視化に向けた第2回ワークショップを津島キャンパスで開催しました。この取り組みは、岡山県の持続可能な発展を支えるための重要なプロジェクトです。
動機と背景
昨年から始まったこのプロジェクトは、学生と地域企業が共に手を取り合いながら、環境問題に取り組むことを目的としています。岡山大学は、地域企業がカーボンニュートラルを実現する手助けを行う実践型教育を展開し、地域社会に貢献することを目指しています。前回の現地見学では、学生たちはシバムラグループのブルーベリー農園や「道の駅かよう」を訪れ、地域産業の実態を学びました。
具体的な活動内容
今回のワークショップには、学生、地域の経営者、岡山県商工会連合会の専門家が参加し、カーボンフットプリント(CFP)を算定する実践に取り組みました。冒頭に天王寺谷准教授が、CO₂排出の「見える化」が企業に及ぼす影響や、その重要性について説明を行い、参加者全員が共通理解を深める時間となりました。
学生たちは、シバムラグループが製造・販売する「ブルーベリージュース」と「ポン菓子」を題材として、製品のライフサイクルとその各段階でのCO₂排出を詳細に分析しました。原材料の調達から製品の販売、さらには廃棄までのフローを整理する作業を通じて、CO₂排出の具体的なメカニズムを理解しようと努めました。
質疑応答のセッション
学生たちは、自身の疑問を積極的にシバムラグループの社員に質問し、実際のデータをもとに討議を進めました。ブルーベリージュースについては、栽培時の農薬使用や輸送手段に関連する質問が投げかけられ、一方でポン菓子に関しては、稲作にかかる肥料や機械の使用について深く掘り下げた議論が展開されました。
今後の展望
ワークショップの終盤では、各グループが作成したライフサイクルフローを基に、今後のデータ収集の方針を共有しました。また、中電環境テクノスの高田氏がJクレジット制度について説明し、将来的なクレジット創出の可能性を示唆しました。学生たちはこの取り組みを通じて、現場の重要性を再確認する貴重な経験を得ることができました。
岡山大学は、年内に今回の討議を基にしたカーボンフットプリントの算定が完了する予定であり、2026年にはその成果を報告する会が開催されます。今年度から進めている「カーボンフットプリントを起点とした価値創造ワーキンググループ」と連携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進していく方針です。地域企業、学生、支援機関が一体となってクリーンな未来を創造するこの取り組みに、ぜひご注目ください。
このプロジェクトは、岡山大学が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた努力の一環です。地域と共に成長し、環境に優しい未来を築く活動に、今後も期待されることは間違いありません。
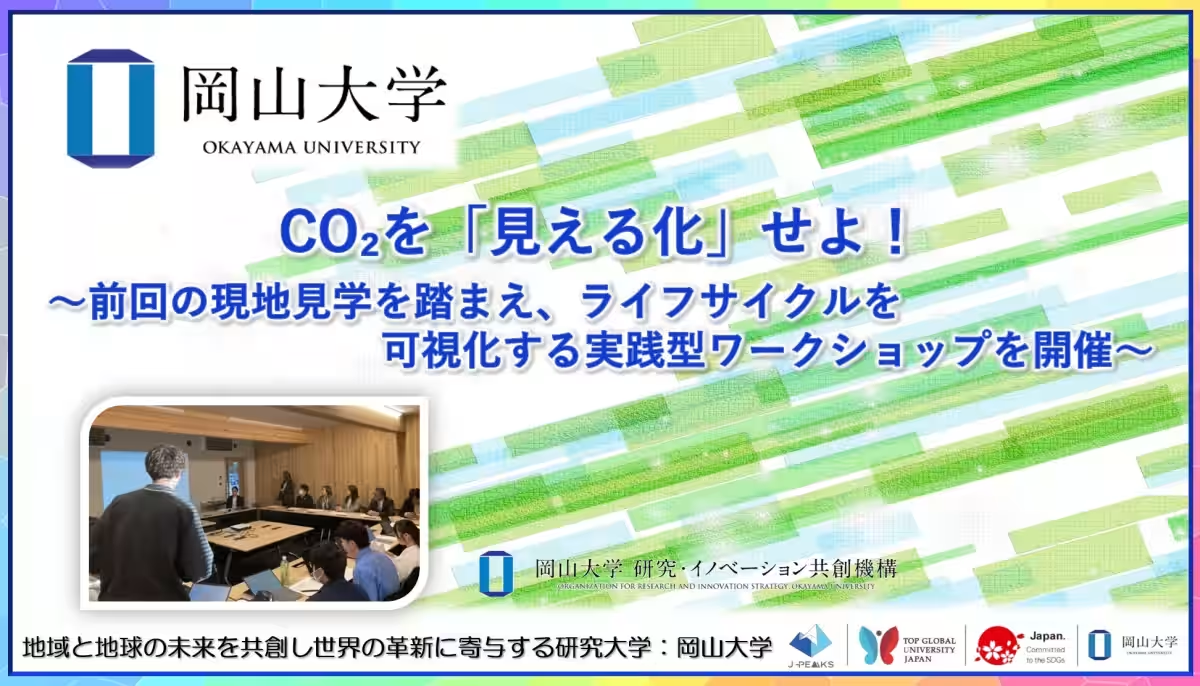









関連リンク
サードペディア百科事典: 岡山大学 カーボンフットプリント 地域企業
トピックス(その他)




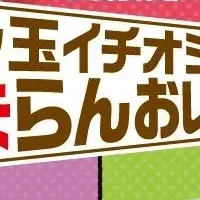



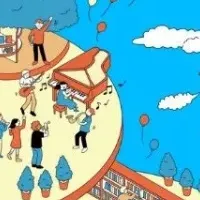

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。