

くら寿司と海と日本プロジェクトが共催するSDGs授業の詳細
くら寿司×海と日本プロジェクトの出張授業
2025年11月13日、宍道小学校にて行われる「お寿司で学ぶSDGs」出張授業は、一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねとくら寿司株式会社が共同で開催します。この授業では、海の重要性や持続可能な食文化について学び、次世代に海の恵みを引き継ぐための意識を育てることを目的としています。
出張授業の概要
この授業では、海と日本プロジェクトinしまねが主催した隠岐諸島での体験学習の様子を収めた動画上映が行われ、地域の漁業状況や海の恵みの大切さが紹介されます。また、くら寿司と連携したプログラムにより、児童たちの理解を深めることを目指しています。
くら寿司の出張授業は、海洋環境や食品ロス、低利用魚の活用についての啓発を目的とした教育プログラムで、全国的に実施されていますが、島根県での開催は今回が初めての試みです。
授業内容
本授業は、以下の3つのパートで構成されます。
1. 海の現状を知ろう
映像や模型を用いて、海洋資源の現状や日本の漁業が抱える課題が解説されます。漁業資源の減少や担い手不足、気候変動といった問題に関心を持つことが重要です。これにより、子どもたちが自分自身の生活にも関連する問題として理解を深めます。
2. お寿司屋さん体験
「お寿司屋さん体験ゲーム」では、児童が実際に注文に応じて寿司を提供する体験を行い、過剰提供や廃棄の影響を肌で感じます。この体験を通じて、食品ロス削減の重要性や資源の有効活用の大切さを学ぶことができるのです。
3. 解決策を考えよう
グループに分かれて、「お寿司を未来に残すためにはどうすればいいか?」をテーマにディスカッションを行います。低利用魚の活用や、ICT技術を利用した食品ロス対策など、実際のくら寿司の取り組みを参考にしながら、子どもたちが独自の解決策を考えます。
隠岐諸島での体験学習
夏に行われた「隠岐めしと歴史探険隊」では、小学生たちが地元漁師から教わりながら、隠岐の海産物について学ぶ貴重な体験をしました。朝廷に献上された歴史を知り、実際にシロイカの捌き方を学習し、自らの手で郷土料理を作る体験もしました。こうした体験を通じて、海の大切さを身近に感じてもらいたいと考えています。
まとめ
この授業は、SDGsの目標12「責任ある消費と生産」、目標14「海の豊かさを守ろう」、さらには目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を基盤に組み立てられています。次世代が海の豊かさを維持し、持続可能な社会を築いていくために必要な学びを提供することが本プログラムの最大の目的です。
授業は他にも松江市内の3つの小学校で行われる予定で、地域全体で次世代の教育に寄与していくことが期待されています。この取り組みを通じて、美しい海と豊かな未来を子どもたちに引き継ぐことができればと願っています。



関連リンク
サードペディア百科事典: SDGs くら寿司 海と日本プロジェクト
トピックス(イベント)

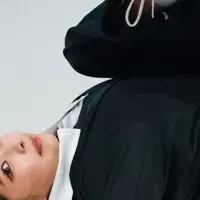

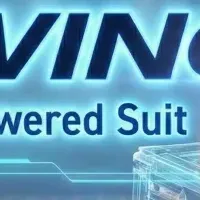



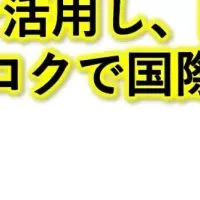
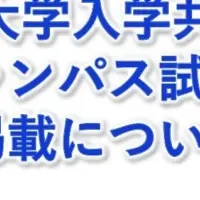
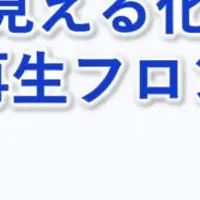
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。