
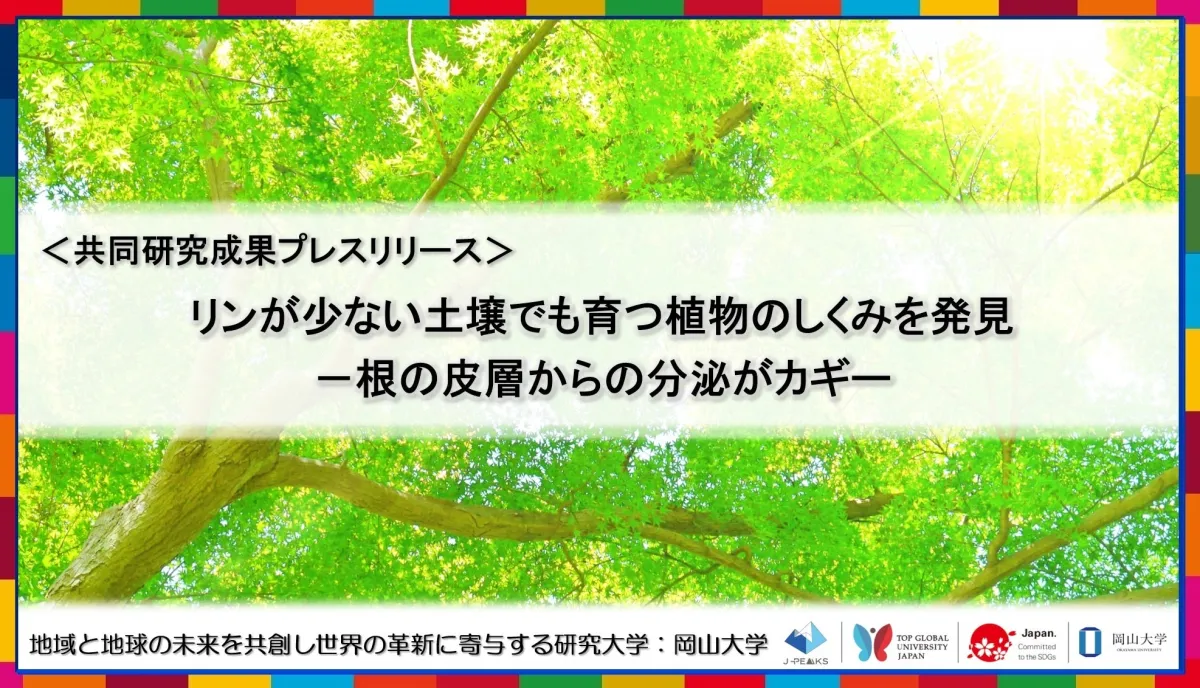
リンが少ない土壌でも育つ!超低リン耐性植物の新発見
リンが少ない土壌でも育つ!超低リン耐性植物の新発見
岡山大学を中心に広島大学、北海道大学、山形大学の共同研究チームが、リンが乏しい土壌でも成長できる超低リン耐性植物についての新たな知見を得ました。2025年5月に発表されたこの研究では、特定の植物がどのようにしてリンを効率的に吸収し、成長するのか、そのメカニズムが明らかにされました。
研究の背景
超低リン耐性植物として知られるのは、南西オーストラリアに生息するピンクッションハケア(Hakea laurina)です。リンが不足した環境に反応して、特別な形態の根、つまりクラスター根を形成することで知られています。このクラスター根は、細かい側根が密集した構造で、根全体の表面積を広げるため、リンをより効率的に吸収する能力を持っています。
これまでこのような根の特性は、主に根の表皮から分泌される成分によって寄与されていると考えられてきました。しかし、研究チームは、根の皮層組織からも重要な分泌が行われていることを突き止めたのです。
研究の成果
研究の結果、クラスター根の特定の部位、特に皮層からリン吸収を促進する有機酸や酵素(酸性ホスファターゼ)が分泌されることが判明しました。これは、根のまわりの土壌にスムーズに拡散され、他の植物と比べて高い分泌能力を持つ要因とされています。興味深いことに、通常の植物が持つ物質の侵入を防ぐスベリン外皮がこの植物には存在しないことが確認されており、これが根分泌能の向上に寄与していると考えられています。
遺伝子の特定と役割
また、研究チームは、クラスター根で特異的に発現するリンゴ酸トランスポーター遺伝子HalALMT1を同定しました。この遺伝子が有機酸の放出にどのように関与しているのか、その機能や存在位置についても詳しく調査が行われています。これまで分野においても解明されていなかった遺伝子と分泌のメカニズムが、新たに明らかになったことで、今後の作物の育成などに応用できる可能性が広がります。
今後の展望
この研究成果は、農業や環境保護の観点からも大きな意義を持ちます。リンが少ない土壌条件での作物の育成が可能となれば、資源を有効活用できる新たな農業の形が模索されるでしょう。また、超低リン耐性植物の特性を利用した持続可能な農業の実践が期待されます。
岡山大学を中心としたこの共同研究は、地域に根ざした科学の進展を示すものです。今後もこの分野の研究が進み、私たちの持続可能な未来へとつながることを期待しています。
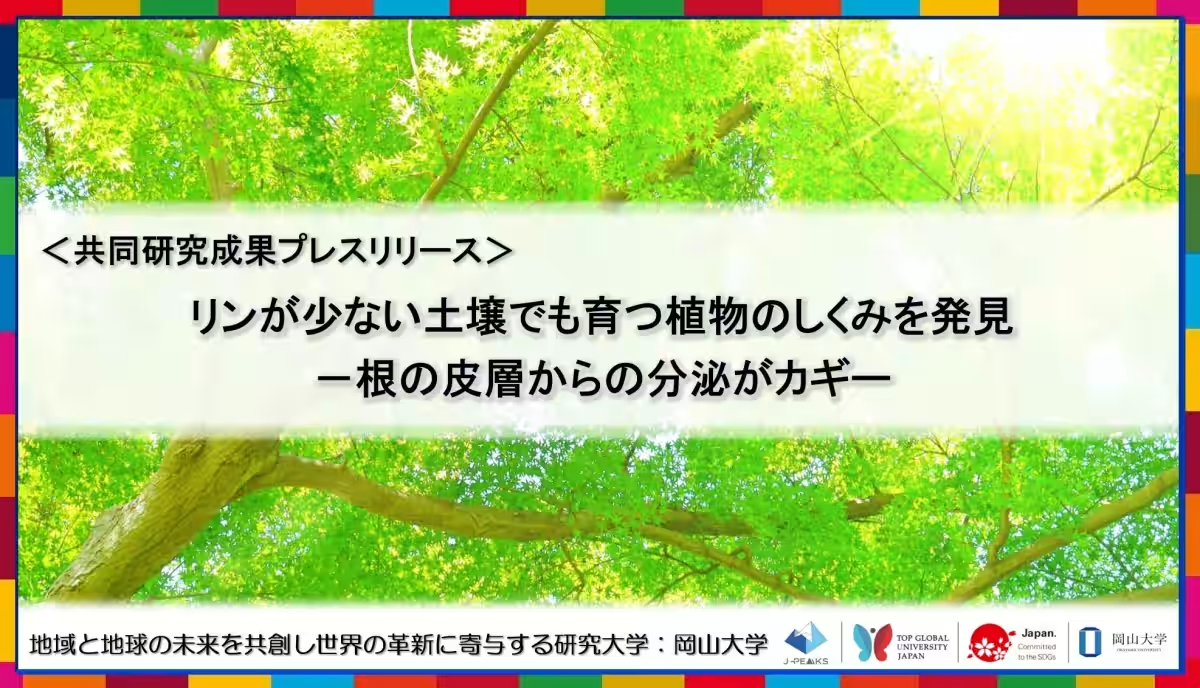



関連リンク
サードペディア百科事典: 岡山大学 超低リン ピンクッションハケア
トピックス(その他)


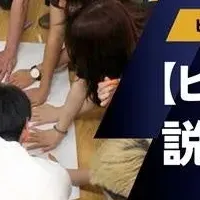




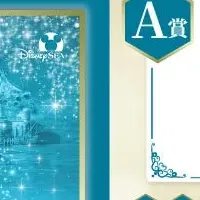
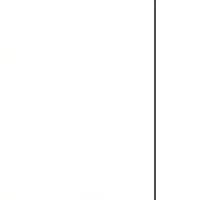

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。