
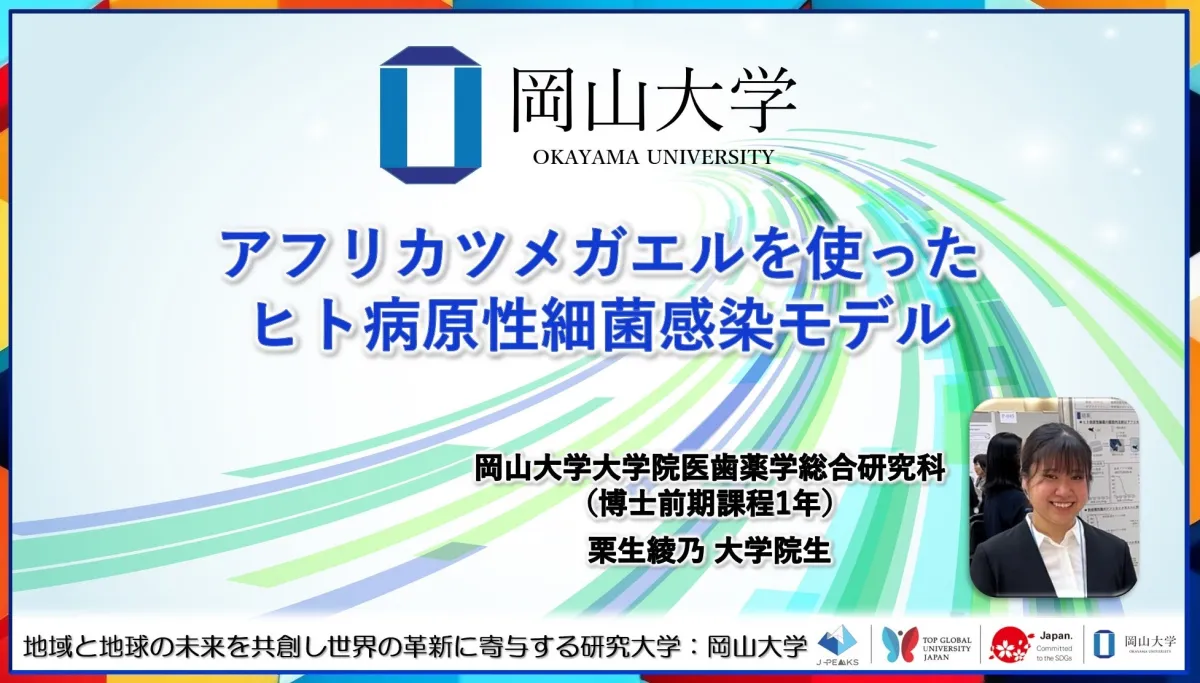
岡山大学が明らかにしたアフリカツメガエルの細菌感染モデルの新研究成果
岡山大学の新たな発見
国立大学法人岡山大学の研究グループは、アフリカツメガエルを利用したヒト病原性細菌の感染モデルに関する画期的な研究成果を発表しました。この成果は、2025年5月1日付の米国の科学雑誌「Infection and Immunity」に掲載され、6月号のカバーイメージに選ばれました。この研究は、細菌感染症のメカニズムを解明し、効果的な治療薬の開発を目指す新たな一歩となりました。
この研究に参加したのは、大学院医歯薬学総合研究科の栗生綾乃大学院生や、石川一也助教、古田和幸准教授、垣内力教授らのチームです。彼らは、アフリカツメガエルがヒト病原性細菌に感染し、それによって致死的な結果をもたらすことを発見しました。具体的には、黄色ブドウ球菌や緑膿菌、さらにリステリア・モノサイトゲネスといった細菌が、アフリカツメガエルに深刻な細菌感染を引き起こし、致死的な結果をもたらすことが示されています。
研究の背景と意義
従来、細菌感染症の研究にはマウスなどの哺乳動物が広く使われてきましたが、その倫理的な問題やコストの観点から、大規模な実験が難しいという課題がありました。そこで、この研究グループはアフリカツメガエルを新たなモデルとして選択し、その有効性を確認しました。アフリカツメガエルは、発生生物学の研究において広く用いられており、哺乳動物に類似した臓器を持つことから、細菌の感染メカニズムの解析において非常に有用なモデルとなっています。
研究結果からは、アフリカツメガエルに対する細菌の致死効果を抑制するために、臨床で使用される抗生物質が有効であることも確認されました。これは、感染症の治療に向けた新たな治療法の開発に貢献することが期待されます。
今後の展望
栗生大学院生は、この研究を通じてアフリカツメガエル内の細菌感染プロセスのさらなる解析を計画しており、病原性に関わる遺伝子を明らかにすることを目指しています。「実験に参加してくれた研究室のメンバーや、論文作成において多大な指導をいただいた先生方に感謝しています」とのコメントを寄せています。
このように、岡山大学の研究は細菌感染症の理解を深め、将来的な治療法の開発へとつながる可能性を秘めたものであると言えるでしょう。今回の発表は、科学分野のプラスに寄与する重要な研究成果です。これからの研究がいかに進展するか、注目が集まります。
この研究に関する詳細な情報は、岡山大学の公式サイトや、発表された論文をご覧ください。
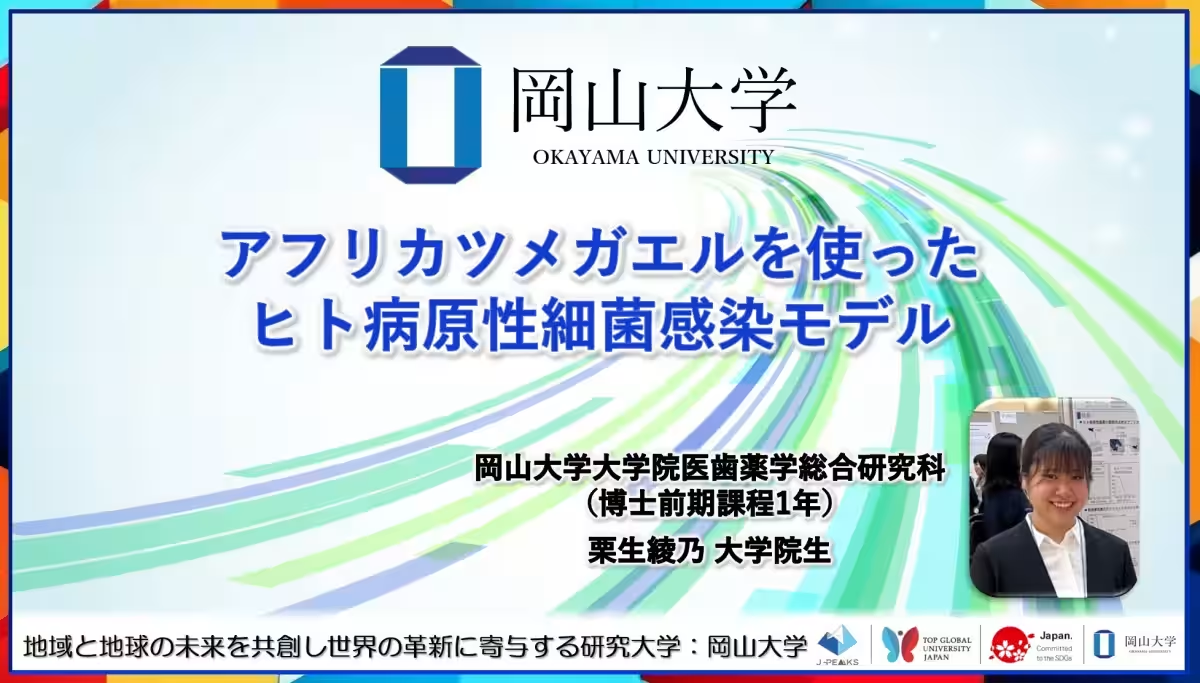

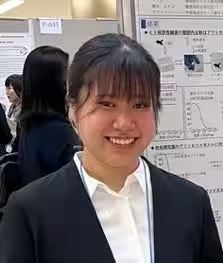
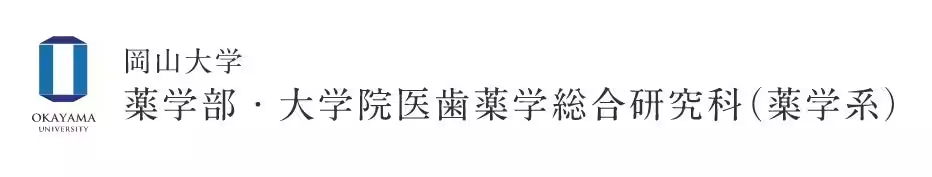


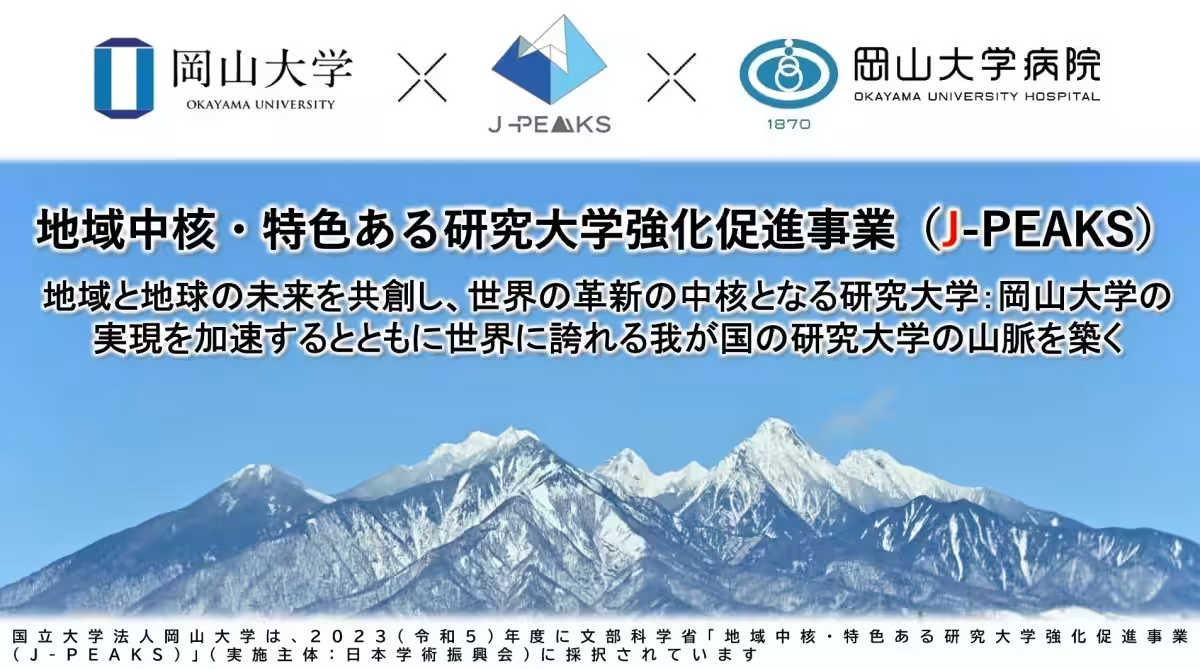


トピックス(その他)




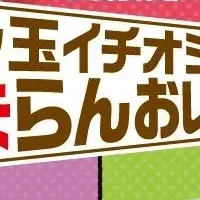



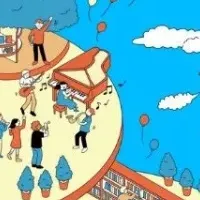

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。