
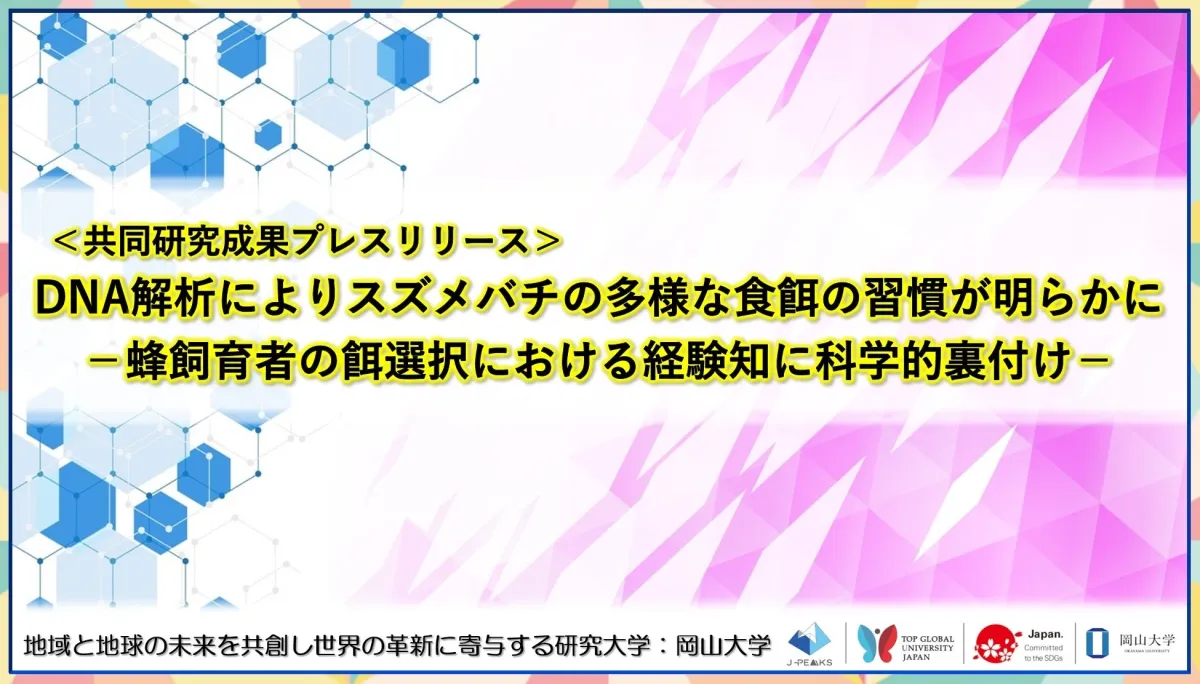
神戸大学と岡山大学が解明したスズメバチの多様な食餌に迫る研究成果
研究の背景
長野県や岐阜県で「蜂の子」として親しまれているシダクロスズメバチ(Vespula shidai)。このスズメバチがどのような食糧を獲得し、食べているかという疑問には長年の関心が寄せられてきました。神戸大学大学院人間発達環境学研究科の佐賀達矢助教と、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の藤岡春菜助教による共同研究が、最新のDNAメタバーコーディング技術を駆使して、この謎を解き明かしました。
研究の成果
今回の研究では、シダクロスズメバチが捕食する餌生物について、324種もの動物を特定しました。これには、昆虫やクモだけではなく、鳥類や哺乳類、さらには両生類、爬虫類、魚類にまで及びます。特に、野生の脊椎動物を食べる習慣があることは、飼育下ではあまり認識されていなかった事実です。この研究により、飼育巣と野生巣の食餌の違いが明らかになり、飼育下で与えられる肉(例えば鶏肉や鹿肉)が、自然な食事とどのように異なるのかを示唆しています。
飼育経験者の声
研究では、飼育経験者を対象にしたアンケート調査も行われ、多くの回答者が、スズメバチの食餌として脊椎動物を見た経験があることがわかりました。実際、多くの人々が「野生巣産と飼育巣産では味が異なる」と答え、その主な理由として与えられる餌の違いが挙げられました。これにより、地域の愛好者たちが持っていた経験知が、科学的な裏付けとして認められたといえるでしょう。
食文化の意義
本研究の成果は、地域に根ざした昆虫食文化が持つ合理性と知識体系を明らかにするものです。スズメバチの飼育や利用において、伝統的な方法と現代の科学がちょうど交差する時代を迎えつつあることを示しています。また、「蜂の子」という貴重な食資源の持続可能な利用に向けて、科学的な研究と地域の伝統が相互に影響を与え合うことが極めて重要であると強調されています。
研究の意義
この研究は、2025年5月14日に「Journal of Insects as Food and Feed」に掲載されました。研究者たちの努力が、既存の知識を深化させ、新たな視点をもたらすことにつながることを期待しています。地域の豊かな文化と生態系の理解を深め、持続可能な食文化の発展に寄与することが目指されています。野生のスズメバチがどのようにしてその独特な食性を保っているのか、今後の研究にのぞみたいところです。
まとめ
この研究により、スズメバチの食習慣を通じて地域の文化や食のあり方についての新たな視点が提供されました。科学的知見と伝統的な技術が共存し、新たな理解を形成することで、地域社会や食文化の未来に大きな影響を与える可能性があります。今後も地域の持続可能性を目指して、様々な研究が進められることを願っています。
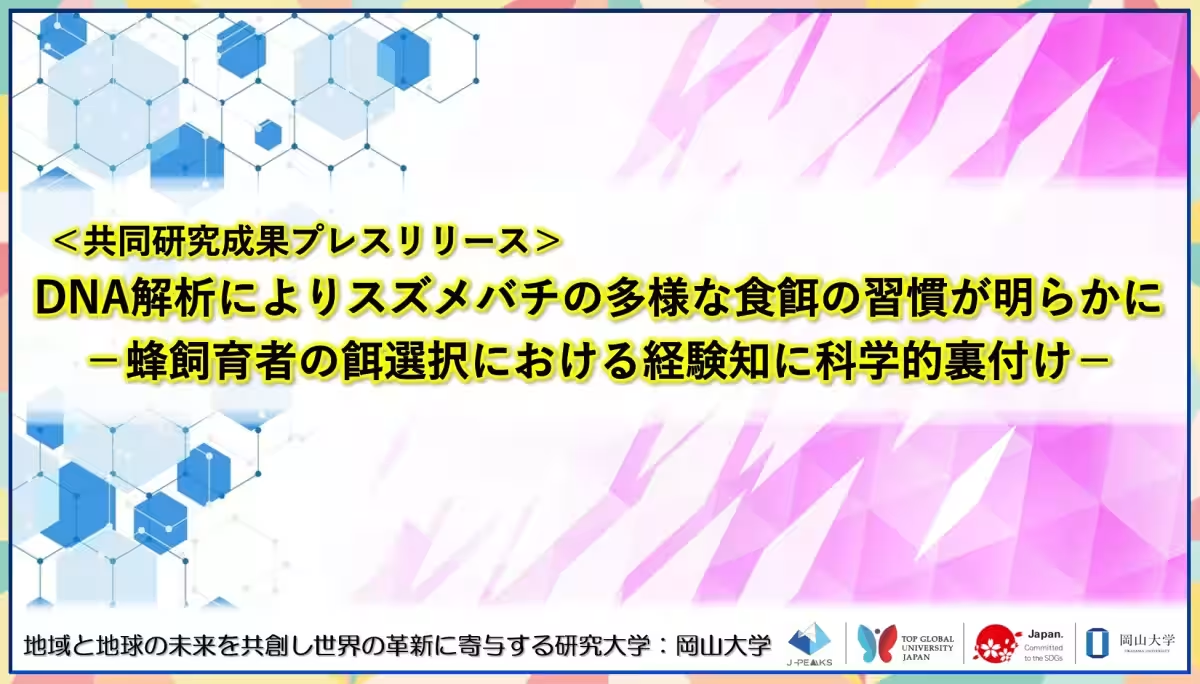






トピックス(その他)


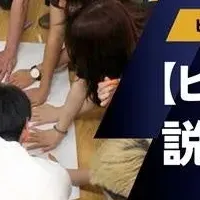




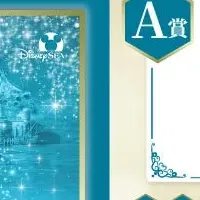
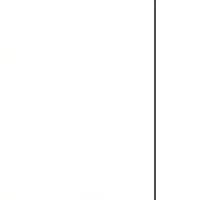

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。